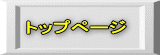

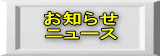
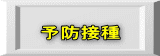
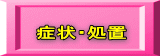
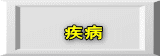
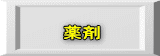
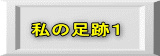
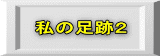
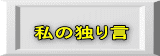
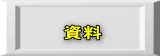
医療関係者以外は内容が若干難かしいかもしれません。
医療関係者以外の方は希望的観測で都合の良い方良い方に物事をとらえないで下さい。
教科書的・標準的な診断・治療に関しては他クリニックや学会のホームページなどを参照して下さい 。
食事後等には37.8℃位になっていることがあります。
・長めの腋下用の電子体温計を使って、ピッピッと鳴るまで測りましょう。途中の掲示される数字は意味があ
りません。できたら腋下に挟んだままもう一度ピッピッと鳴るまで測ってみましょう(2回目のは実測値に近い
値です)。
・発熱は病原体に対する防御反応です。熱を下げる事でその防御反応の一部が抑えられる事が判っていま
す。確かに以前は熱があればともかく熱を下げていました。しかし、原則として熱は下げる必要はありませ
ん。
・熱が高いと頭につくから熱を下げるように言われていました(熱が高いから脳症になるのではなくはなく、脳
症だから熱が高いのです)。熱性けいれんは熱が上がる時に起こすのであり、熱が高い時に起こすので
はありません。熱性けいれんだったら後に後遺症を残すことはありません。また解熱剤を使用することで
熱の上がり下がりの頻度が多くなり、熱性けいれんをおこす機会も多くなります。
・大人は38.0℃位あると仕事も出来ませんし、食欲もなくなります。でも解熱剤を使って熱を下げる事で仕事
も通常位できますし食欲も戻ります。その様な症状がある時だけ解熱剤を使用してください(かもしれない
・だろうでは使用しないでください。熱があるのですから多少は元気がないのは当然です)。幼児では走り
回って元気に遊んでいても熱を測ると39.0℃位あることがよくあります。その様な熱は下げる必要がない
のです。また40.0℃あってもぐっすり寝ていれば起こしてまでして熱を下げる必要はないのです。
・高熱でつらそうにしている時だけ解熱剤を使用しましょう。
・なるべく経口の解熱剤を使用しましょう。(坐剤は腸の粘膜から効率よく吸収されますが、その分急激に解熱
しますがその分負担が大きいのです。)
・吐き気がある時伴っている時。このような場合は経口薬ではなく坐剤を使って熱を下げましょう。
・乳幼児(2歳以下)には冷却シート(熱さまシート、冷えピタ)を使用してはいけません。冷却シートは当たって
いる所の表面の皮膚温しか下げず、体温まで下げない事は報告されています。それよりも冷却シートがず
れて口と鼻を塞いで窒息した乳児の報告があります。その子は高度 の低酸素脳症になってしまいました。
・保冷剤や氷嚢を頭に当てるのも乳幼児では控えましょう。冷たすぎても自分で払いのけることができないから
です。凍傷になったり、冷却シートのように口や鼻を塞ぐ危険性もあります。
・寝ているのに体温を測ってみると高かったからといって、起こしてまでして解熱剤を使わないでください。
・「考え方」で述べたように元気なのに体温計で体温を測ると高いからと解熱剤は使わないで下さい。
・熱がないのに解熱剤は使わないで下さい。分服薬(1日3回食後等といった定期的に服用する内服薬)として
処方されている場合は頓服薬として処方してもらいましょう。ただし、鎮痛剤として使用する場合は別です。
・嘔吐は子どもの日常よくある病気の症状の中で対処の仕方によっては重症化し易くなります。見た目で尋常
ではないと分かる”けいれん ”とか”チアノーゼ”(循環が悪くなって唇が真っ青になる状態)は危急を要す
ることが多いのですぐ医療機関に掛かりますが、子どもの嘔吐はよくあるので軽視しがちです。昭和30年
代までは乳幼児の死亡原因のトップが吐き下しであったことを忘れてはなりません。
・嘔吐は[イ]中枢性嘔吐、[ロ]末梢性嘔吐に大きく分類できます。
[イ]の中枢性嘔吐は脳出血、脳腫瘍脳髄膜炎等で脳圧が高くなって嘔吐とするものです。
[ロ]の末梢性嘔吐は胸腔・腹腔臓器からの刺激による嘔吐(この項ではこのなかの消化管臓器からの刺
激による嘔吐について述べます)、口腔・咽頭頭部・機械的刺激と迷路刺激(めまい等による嘔吐)があ
ります。子どもで日常よくあるのは口の中に食べ物を入れすぎたり、口の中に指を突っ込んで 嘔吐する
ことはよくあります。また咳をした拍子に嘔吐したり、転んだ拍子に吐いたりします。元々乳児は口に物
が触れると吸いつくという原始的な 吸啜反射があり、その反射によって授乳しています。満腹になって
もこの吸啜反射は残ります。
その為、飲み過ぎの安全弁として食道と胃の間にある 逆流を防ぐ弁(噴門)がルーズになっているの
で、子どもは何かの拍子に吐いたりすることがよくあるのです。この度様な場合は寸前(少なくとも2 ~
3時間前に摂取した)ものしか吐物の中に含まれていません。咳をした拍子に吐いたりする場合は、一
回の授乳量、飲食量を少なめにしましょう。
・消化管臓器による嘔吐は腸捻転とか機械的閉塞による嘔吐は嘔吐が止まりません。全身状態が悪く吐物も
黄色・緑色になってきます。夜 中でも医療機関を受診し、診断・処置が必要です。一方日常的によく遭遇す
るのは殆どが感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス等)です。病初期は嘔吐が前面に出ます。消化管
の蠕動運動(消化管の筋肉が伝播性の収縮波で食物等の消化管内容物を下部への移送する運動)が停
止・低下して嘔吐を誘発します 。吐物も5~6時間から12~18時間前に摂取したものや何度も嘔吐した場
合黄色・緑色のものを嘔吐するようになります。この消化管の動き(蠕動運動)が停止・低下している時期
に吐かさないことが肝要です。実際は脱水が怖いからと動いていない胃に水分を入れ(水分を飲ませ)て
何度も嘔吐さ せている例が多くあります。
・原因が何であれ、嘔吐を何度も繰り返すことで水分も喪失しますが、強酸性の胃酸(pH1.0-2.0)が体から喪
失します。その為脱水だけはなく、体液はアルカリ性に傾きます。また胃液により食道が傷つき出血するこ
とがあります。その血液が嘔吐を誘発するようになります。
・ともかく吐かせてはいけません。
・吐き始めてからの時間を経ているか?。脱水があるか?。3才以上か?。によって対処法が違います。以前
この"吐き下し"は”おなかを壊した"”食べ物に当たった"など消化管の病気の様に言われていましたが
現在はウイルス(ロタウイルス,ノロウイルス,アデノウイルス等)や細菌(カンピロバクター,病原大腸菌等)の
感染症という事が判っています。ウイルス性のものは病初期特に半日は(消化管の蠕動運動が低下ないし
欠如している為)吐きやすい状態にあります。中には半日前からの発症で半日前に摂取した食べ物を嘔吐
する事で発病する事もあります。このような状態の時口から物を与えると水でも嘔吐します。口から物を与
えてはいけません。「吐いても吐いても与えなさい。」「吐気が強い時でも母乳は与えても構いません」とガイ
ドラインに沿って指導している医師がいますが、嘔吐することにより体液のバランス(pH)が崩れることによ
りより吐きやすくなります。
水分を与えるタイミング、与え方
研修医向けのガイドラインでは経口補水(ORS)は早期に開始になっていますが消化管の動き(蠕動運
動)が ない時期は経口補水開始は無理で吐かせるだけで、与えてはいけません。
・吐いた後1時間は欲しがっても我慢させましょう。うがいも控えましょう(飲んでしまいます)。
・胆汁(黄色い汁)やコーヒー残査様物(嘔吐による食道からの出血や胃粘膜からの出血)を嘔吐した場
合は、家で様子を見ないで夜中でも医療機関にかかりましょう。
・複数回嘔吐している場合や嘔吐した中身が3時間以上前に摂取した食物残渣の場合は、医療機関で
腸管通常がある程度動いているか確認して下さい。そして必要なら嘔吐止めの処置をして貰って下さ
い(経口処置以外の方法で)。
・脱水がある場合は高Na低糖濃度の”OS1”や”アクアサポート”を使用。吐き始めや脱水がない場合は
弱Na高濃度で糖非高濃度の〝アクアイト””アクアサーナ””アクアソリタ”ですが、3歳以上は低Naで
すが高糖濃度の”ポカリスエット””アクエリアス”が適切かもしれません。
1.最初は15ml(小さじ1杯)を与えます。それ以上欲しがっても与えない。(吐き気止めの坐剤(ナウ
ゼリン坐剤あるいはドンペリドン坐剤を入れた後は1時間以上後)
2.15分経ても吐き気がなければもう一度15ml与えます。
3.15分経ても吐き気がなければ30ml与えます。与え始めてから6時間まではこれを繰り返します。
(嘔吐した回数、吐き始めからの時間、全身状態、吐き気の程度やその児の既往歴により多
少変わります)
4.3歳以上で自家中毒(アセトン血性嘔吐症)の既往のある児は3回水分摂取ができた後、1度だけ
砂糖(合成甘味料や飴はダメ)を大さじ2杯位与えて下さい(水に溶かすと水の量で吐く場合が
あるのでそのまま)。自家中毒が加わっている場合嫌がりますが頑張って与えて下さい。既往
のない児でも与えてみて下さい(嫌がったら与えた方が良いでしょう)。3歳未満は不要です。
5.1~4がクリアできれば、45ml.60ml.80ml.100ml.と30分毎に増量(年齢により目標が変わりま
す。1才未満はMaxは60~80ml、それ以上は80~100ml
6.この間は沢山与えて水分を補充するというより、腸管が動き出すまで吐かさないで現状を維持して
時間稼ぎをすることが大切です。
7.無理やり与えないよう。
8.お茶やジュースは与えてはいけません。(吐物で判断できなくなります)
9.これらをすべてクリアできたら次回からミルクならいつもの6~8割程度、母乳なら片方だけ、離乳
後や幼児の場合は最初は消化の よさそうなものをいつもの5~6割り程度与え、共に大丈夫
なら食事の中身はいつものもので結構ですが、量を7~8割以上は与えないようにして下さい(
水分も量の内です)。
・黄色いもの(胆汁)やコーヒー様のものを嘔吐している場合は夜中でも医療機関を受診してください。
痢。乳糖等の吸収障害による下痢。他に試験前等によくある心因性の下痢。食事の過誤による下痢。そ
の他の原因によるものがあります。
・一番多い感染によるものは病原菌や毒素などを排泄する行為・腸管動きを更新させて内容物を洗い流して
腸管を掃除しているのです。自分自身で病気を治そうとしているのです。薬で下痢を止めてはいけないの
です。
・下痢は体から水分が出ていく(奪われる)のでその分の水分を補充しなければなりません。
・原因を確認し治療に結び付けるには便を調べなければ分かりません。おむつのままか紙コップかオマルで
直接取ったものを持参してください(水洗便所の水に浸かったものや触れたものは検査に適しません)。
昔から日本では発熱した時や下痢の時は「おかゆ」と言われてきましたが、間違っています。食欲があれば食
欲に任せて欲しいものを食べた方が良いのです。但し好き嫌いは別として食べたくない物は無理に与えないで
下さい。
・日常よく見られる下痢の感染性下痢の場合、原因が何であれ下痢をしていても吐き気がなければ(収まれば
)、食事内容を普段と同じものを与えなさい。・・・という勧告は1990年代から欧州小児栄養消化器肝臓
学会、米国小児科学会から何度もでています。最近は米国疾病予防管理センターからも出されている。
しかし、日本では消化の良いものから少しずつ、3分粥、5分粥など、またミルクを薄めてなど今だ下痢の
時の食事として日本の育児書や栄養の本に載っていますが現在は否定れています。食餌内容は前述。
乳製品は乳糖不耐症の状態であれば乳製品(乳糖)を摂取すると下痢が激しくなるが、そうでなければ除
外する意味がない(乳糖不耐症の項を参照)。
・最近は下痢の時は電解質液とかコマーシャルで宣伝していますが、糖分が高いので食欲を減退させ ますし
糞便を柔らかくします。ある程度食欲があったり、みそ汁やお澄ましを飲めておれば、水分の補充は水や
お茶の方が適しています。
![]()
と塩くどいものが欲しくなります。疲れると甘いものが欲しくなります。体中の成分の不足しているものを摂
りたくなります。ですから好き嫌いは別として欲しがるものでは与えるようにして下さい。過べ過ぎは別で
すが、熱とか下痢の場合日本では「御粥さん」と相場が決まっていましたが、現在は食欲があれば好きな
ものを与えても構いません。
2.5の他埃なども一緒に吸い込みます。細菌の残骸とか埃等は粘膜の粘液産生細胞から分泌される粘
液で包まれ、粘液上皮細胞の線網が働き、粘液と異物を喉の方へ押出します。 それを纏めて排泄する
のが「咳」なのです。 そうして空気の通りを良くしている訳で「咳」は空気が通りやすい様呼吸面積を広げ
ようと直しているのです。痰が切れるような咳が最後にあってから咳は止まるはずです。ですから原則とし
て咳は止めるのではなく、水分を痰が飲ませて痰をサラサラにして(粘調にならないよう)、痰を切れやす
い様にするのが大切です。副鼻腔・鼻孔では喀痰が鼻汁であり、咳嗽がくしゃみです。
・咳が激しいと夜中その咳で目を覚ますことがありますし、その咳の拍子で嘔吐することもあります。この場合
嘔吐止めの処置をしても意味がありません。
・咳や鼻水が出ているから風邪(ウイルス等の感染により粘膜の炎症)をひいている事もありますが、上に述
べたように粘膜の過敏性(粘膜の正常な反応)で出る場合も多いのです。以前幼稚園の問診票をまとめ
た事がありますが。咳が朝晩出やすいと答えが524人中166人で4人に1人、鼻汁は524人中252人で2
人に1人、咳か鼻汁かどちらかがある児は524人中289人で半分以上の児が咳か鼻汁が出易いと答えて
いました。
して使用。③臓器移行性を考慮する事。④新生児は蛋白結合率を考える事。⑤疾患の重症度を考える事。⑥
Narrow spectrumの抗菌剤を使用する事。⑦抗菌剤の副反応と年齢特異性を考える事。⑧薬剤の体内動態
を考える。‥‥事だと思う。ここでは①を中心に私の感染症専門医(感染症学会の専門医は取得していない)
としての歴史と共に論じたい。抗菌剤適正使用の各項目は本来抗菌剤を使用する医師なら当然考慮されてい
る事柄と思っている。
私が医者になった頃はセファロスポリン系が出始め、ABPCにAMPCが加わった頃でまだ肺炎球菌もインフ
ルエンザ桿菌も耐性菌は殆どない時代であった。その後1978年J.PediatricusにAntimicrobacterial therapyの
Reviewが出、またHL MoffetのPediatric Infectious Disease でBaseを学んだが、その頃と違って現在は各種
抗菌剤の台頭とそれに伴う基礎的抗菌剤の市場からの消滅そして耐性菌の増多が世界的な問題になってき
た。日本でも厚労省が後押しをして耐性菌増加防止に向けてのキャンペーンを張っている。不要な抗菌剤、不
要な広域の抗菌剤を使用しないというのは理解できるが、全体として使用するのが誤(悪)、使用しないのが正
(良)という論調には違和感を感じざるを得ない。
・細菌感染症の診断。
感染症であると診断する場合、起炎菌の存在証明と生体の反応証明をして初めて感染症と診断でき
る。細菌性の場合抗菌剤を投与する事で菌が消滅してしまうので(起炎菌がそうであって呉れれば良い
が?)投与後検査しても起炎菌は証明できない。尿路系、消化管系、呼吸器系の培養は常在菌が多数
あり、又病原菌自体も常在菌の場合があり(不顕性感染もありまた溶連菌は普通の人でも3~5人に1人
は保持している)、培養等で後日(あるいは検査当日)にその結果の解釈は難かしい。
一方生体の炎症性の反応を証明して細菌感染症と診断できる。尿、糞便の白血球の集塊あるいは
増多や、溶連菌特有の出血性の粘膜診等である。通常は細菌感染症は白血球が増多に傾く。大人は
8000/μlまでは正常であるが乳幼児は23000/μl位までは正常である。又炎症反応を反映すると言われ
ているCRPは1.0mg/dl未満が正常値であるが、4.0~5.0mg/dlあれば細菌感染としている報告もある。
CRPは細菌感染に特異的なものではなく、膠原病やその他の疾患でも高くなる。ウイルス感染症でも多
少は高くなる事がある。これらは生体の反応としてのCRPである。細菌の感染による生体の反応であり、
若干のタイムラークがあり、状態が良ければ1日経過してから検査をしている。新生児は発熱した場合敗
血症を常に考えねばならいし、早く治療を開始しなければならない。その為はΔCRP(微量の時間CRP増
加量)で判断している。IDATEN(日本感染症教育会)の岩田氏らはCRPは当てにならないと言っているが
、一方で陽性のCRPは考慮すべきとも言っている。大人(Ex高齢者)でのこのタイムラークの問題であろう。
使用しなくても治癒した…というのは細菌感染症を否定するものではなく、細菌感染症の自然治癒も含ま
れていると思われる。また、担癌患者や免疫不全を伴っている患者あるいは新生児の場合には感染に
対し抵抗力が弱く、そのまま重症化するので炎症の程度が低くても、その兆候がある場合抗菌剤を使用
している。確かにウイルス感染症でも多少特に初期にCRPが高くなることもあり、例外的にアデノウイル
スは高く出る事が多い。発熱でWBC,CRP等で正常ではない値の場合、ウイルス感染症だけでその範囲
内なのか、細菌の感染があるのか、細菌の感染があっても自然治癒する程度なのか、我々小児科医は
いつも悩んでいる。我々小児科医は手遅れになった細菌感染症を沢山診てきている。もう1日早く受診す
れば助かったのに!後遺症残さなかったかもしれないのに!といった症例を経験しているはずである。
さて、現実に戻ろう。我々小児科医が診察して細菌感染症を疑いWBC,CRPもそれを支持する値なのに
、自然治癒する可能性が高いから抗菌剤を投与しないで経過を看れるだろうか。自然治癒するかどうかの
基礎データーとして年齢、免疫不全の状態にあるか、疾患の重症化率、細菌の毒性が基礎にあり、そし
てCRPの値などで抗菌剤を使うか使わないかを判断し、さじ加減をするのが医師である。しかし、医師の
個人差がある。私は昔の事を知っているの為だろうと思っているが、感染を確認したら重症化する前に
軽い程度使用しているのだろう。しかし感染を確認しないで使用する事はない。
・AMR運動
前に述べたように私が医者になった頃はABPCにAMPCが市場に加わった頃でまだ肺炎球菌もイン
フルエンザ桿菌も耐性菌は殆どない時代であった。その後多数の抗菌剤の使用により、耐性菌の頻度
が年毎に高くなり、人類の将来にも関わる位に増えてきた。耐性菌の増加は不要な抗菌剤の使用と必要
以上の広範囲抗菌剤の使用が耐性菌の増加をもたらしているので、国際的に不要な抗菌剤の使用しな
いという運動である。厚労省のその日本版を読んでみると、疫学的、統計学的に少ないからこの疾患は
抗菌剤を使用する必要がないという表現が多い。その為抗菌剤を使わない方が善、使う方が悪というよ
うな風潮が流れている。前項で述べたように我々小児科医はその例外的患者が抗菌剤の使用が遅かっ
た故に重症化した症例を沢山診ている。疾患名は臓器別の病名であり、同じ○○炎でもその原因として
細菌性、ウイルス性では治療法と経過の見方が全く違う。検査をしなくてあるいは炎症のデーターが(-)で
経過を診ている間はともかくとして、検査をして細菌感染症を疑わせるデータ~の場合、その程度・全身
状態・年齢・免疫状態、発熱後の経過時間等から、自然治癒の可能性の有無、重症化の可能性等を考
慮して主治医が抗菌剤の使用を判断した場合、誰も文句のつけようがない。
AMR(抗菌剤の薬剤耐性)運動では抗菌剤を使わない方が善的な表現をしているが、感染である事
を確認せず(検査せず)に抗菌剤を処方するよりもずーっと良心的であり、科学的であると思う。
[参考文献]
Heinz F et al. Antimicrobial therapy in infants and children: Part I. Review
of antimicrobial agents. J Pediatr 93:337–356.1978
George H et al. Antimicrobial therapy in infants and children: Part II.
Therapy of infectious conditions. J Pediatr 93:357–377.1978
Fisher RG et al ed. Moffet HLed Pediatric Infectious Disease 5rd ed.Philadelphia,2017
厚生労働省健康局結核感染症課. 抗微生物薬適正使用の手引き第二版 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000573655.pdf(2020.8.11参照)
![]()
食事の開始、希釈乳の不使用(1995年代より)、乳糖除去乳の不使用(1995年代より)、BRAT食(バナナ+米+
リンゴ+トースト=消化の良い食物)の不使用(1995年代より)等で吐き気が収まれば早々普通の食事に戻した
方がよいという事になった。しかし、以前のペーパーは他施設のものもあり、また現在の様にロタウイルス、ア
デノウイルス、ノロウイルスが迅速に外来検査できる以前の時代で、それら夫々固有の下痢の期間が違う。そ
れらを分別しデーターを取り直せばもっときれいなデーターになるのであろう。乳糖は絨毛~乳糖分解酵素の
観点から理解はできるが、タンパク質、脂肪を制限っするにはその分解酵素と吸収の面からの基礎データー
が必要であろう。確かに胃貯留時間は脂肪>タンパク質>炭水化物の様だが吐き気(蠕動運動の低下)が収
まれば関係性は薄いと思われるが、モリチン等の報告は殆どない。この辺りは私の勉強不足かもしれないが
ウイルス性腸炎による(キモ)トリプシン、リパーゼなどの分解酵素の動態や酵素によって分解されたアミノ酸、
脂肪酸の吸収に関する感染下の報告もない。下痢が遷延しての脂肪便、たんぱく喪失性腸症等の報告もな
いので多分生物として欲しがれば制限は不要なのだろう(私見)。AAPやESPGHANの母乳に関してどのような
時も(嘔吐している時も)構わない?は根拠がないし、宗教的と思っている(私見)。
[参考文献]
Committee on Nutrition. Use of Oral Fluid Therapy and Posttreatment Feeding Following Enteritis in Children in a Developed Country. Pediatrics.75:358-361. 1985
Provisional Committee on Quality Improvement,Subcommitee on Acute Gastroenteritis. Pediatrics. 97:424-435,1996
Wker-Smith JA et al.Guidelines preparated by the ESPGAN Working Group on Acute Diarrhea :Recomendations for feeding in childhood gastroenteritis, J Pediatr Gastroenterol Nutr 24:619-620. 1997
として開発され、沢山の命を救命できた。コレラの糞便のNa濃度が高いため経口補液のNa濃度が90mEq/l
で良かったが、欧米でRotaVirusの吐け下し に使用すると高Na血症の報告がなされ、50mEq/lになった。私が
知ったのは東京女子医大の山口先生の紹介論文だった。一般化されたのはMMWRを翻訳された2005年過ぎ
である。商業広告の役割も多かった。しかし市販のNa濃度50mEq/の補水液はMMWRに記載してあるように
rehydration用であり、脱水症になっていない場合は適応できない。又、paralytic ileusの状態の時
(Gastroenteritisの初期)も使用できない。少なくとも経口補液をする場合は少なくとも酸塩基平衡や輸液の理
論を熟知した上で実施されるべきである。経口補液でも全身状態からとウイルス性腸炎の病期判断そして所
謂自家中毒状態の有無により脱水のStage判断により初 期輸液・補修輸液・維持輸液のORSの選択に至
るべきであり、一回嘔吐しただけで脱水もないのにOS-1を使用すべきではないし、Paralyticなphaseで経口
摂取を開始すべきではない。また、母乳ならどんな段階でも摂取可というのは原本から言われているが疑問で
あり、少なくともParalyticなphaseでは不可であるはずである
ParalyticなphaseではNPO。(薬剤に関係なく)paraltic phaseの解除期で脱水がなければ経口維持輸液のア
クアライト、アクアサーナなどNa濃度が35-40mEq/lのもの、脱水があればOS-1等Na濃度が50mEq/l位にも
のを使用し少量より経口摂取開始(脱水の評価に着衣で良いから平生から日常的に診察毎に体重を測定て
おくと便利)。嘔吐が収まらない場合は時を失せずに経静脈輸液。
★私の経口輸液(ウイルス性感染性胃腸炎)★
・問診にて発症時間を想定(吐物を摂取した時間/最初胆汁様吐物の場合その約6時間位前)
・Paralytic phase(問診と腸雑音で)
五苓散坐剤挿入後30~60分から脱水ある場合OS-1、脱水(-)の場合アクアライト・アクアサーナ
・アクアソリタ等維持経口補液(Na:35-40mEq/l)のもので開始(15ml/α)嘔吐なければ30分後再度
同量経口摂取。嘔吐なければ30分後30ml、30分後45ml・・・・と増量、OS-1の場合補修量の1/2を
摂取した後は維持経口輸液に変更し、通常経口摂取量の3/4まで増量できれば固形物を少しずつ与
える。(夜間になる場合は就寝で中断、翌朝ドンペリドン坐剤 を挿入後1時間経てから中断前の量か
ら開始)
[参考文献]
山口規容子. 小児下痢症の輸液療法. 小児内科. 1982:14:995-1001
中尾弘. 脱水症. 豊原清臣等編. 開業医の外来小児科学第3版. 東京. 南山堂. 1997. 153-166
King C.K.et.al. Managing Acute Gastroenteritis Among
Children. MMWR 2003:52:RR-16:1-16
Report of an ESPGAN Working Group Recommendations for composition of oral
rehydration solutions for the children of Europe. J Pediatr Gastroenterol
Nutr 14:113-115. 1992
![]()